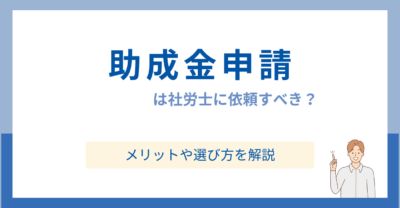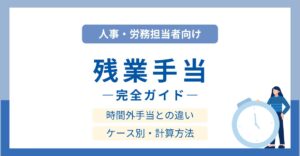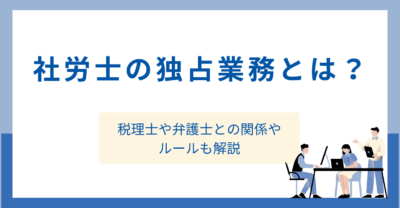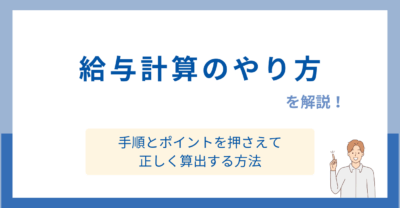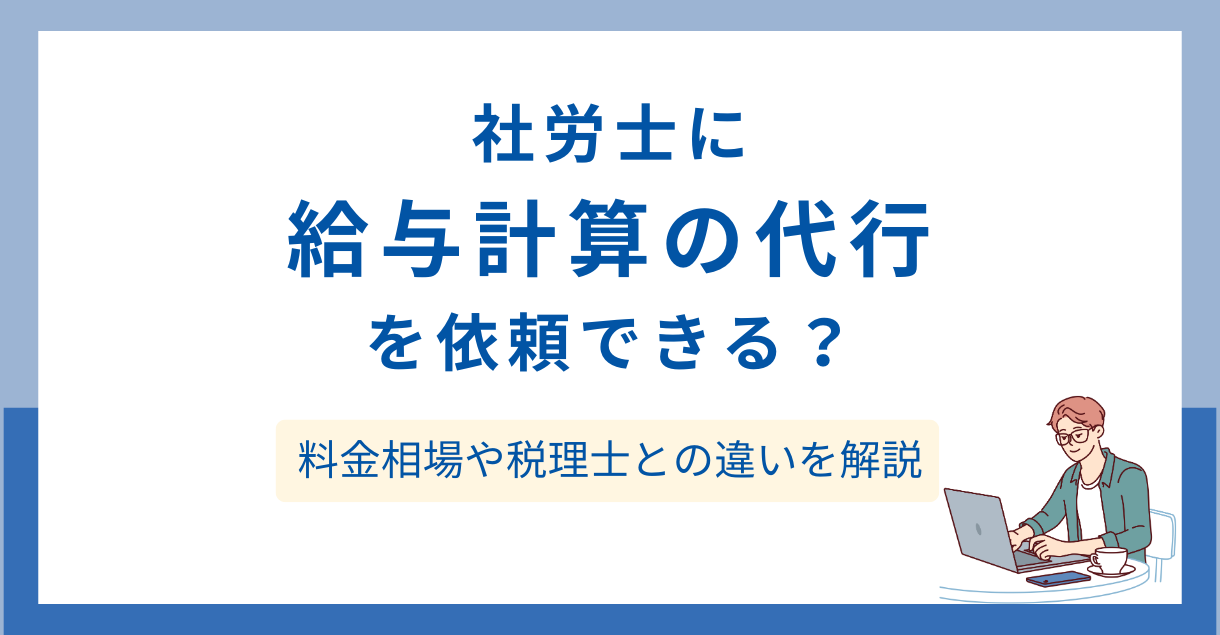
社労士に給与計算の代行を依頼できる?料金相場や税理士との違いを解説
毎月の給与計算は、社労士(社会保険労務士)に依頼すると、業務負担の軽減や採用・育成コストの削減などにつながります。従業員数が多くなるほど毎月の業務量も増加するため、早めの検討がおすすめです。
また、給与計算は税理士に依頼することもできますが、社労士とは得意分野が異なりますので、それぞれの違いや強み、メリットを理解して、適切な専門家に相談することが重要です。本記事では、社労士に給与計算の代行を依頼するメリットを解説します。ぜひ参考にしてください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
給与計算の代行を依頼できる「社労士」とは
社労士は、労働・社会保険に関する法律を専門とする国家資格者です。主に、以下の業務内容を依頼できます。
- 行政機関への手続き代行(1号業務)
- 帳簿などの書類の作成(2号業務)
- 人事労務に関するコンサルティング(3号業務)
給与計算は、基本給や残業代、各種手当の算出だけではなく、控除額や社会保険料の計算まで複雑な処理が含まれます。社労士は、複雑な給与計算を代行するのみならず、労務全般に関する幅広い知識と実務経験を活かして、企業を支援してくれます。
社労士に給与計算の代行を依頼するメリット
給与計算の代行を外部の専門家である社労士に依頼すると、以下のような多くのメリットがあります。
- 自社の業務負担を軽減できる
- 採用・育成コストを削減できる
- 法律に準じた処理や法改正にも対応できる
- 労務・社会保険関連業務も別途依頼できる
給与計算の業務負担が減ることはもとより、ほかの業務もあわせて任せられるメリットもあるため、確認してみましょう。
自社の業務負担を軽減できる
社労士に給与計算の代行を依頼すると、自社の業務負担を軽減することができます。給与計算は以下の内容が一般的とされていますが、もちろんすべて社労士に依頼することが可能です。
- 勤怠集計
- 各種手当および控除の計算
- 社会保険料の計算
- 各種税金の計算
- 給与明細の発行
さまざまな専門的な処理を従業員数に応じて行わなければならない給与計算は、時間と手間のかかる作業です。しかし、社労士に依頼すれば、給与計算に費やす労力を削減できるというメリットがあります。
なお、給与計算は締日から支払日までに処理を行わなければならないことから、毎月特定の時期に業務が集中しやすくなります。社労士に依頼することで給与計算に割く時間を削減でき、業務を平準化できます。
また、給与計算のミスは従業員の信頼を失うことにもつながります。専門家である社労士に依頼することで、ミスに対してリスクを予防する効果が期待できます。
採用・育成コストを削減できる
給与計算の代行を社労士に依頼することで、採用や育成コストを削減できるメリットもあります。給与計算は担当者に依存しやすく、担当者が退職または異動となった場合に新たな人員確保が必要です。
また、確保した人員に対して、教育研修を行う必要もあることや、引き継ぎの手間も発生します。このように、さまざまな懸念事項がありますが、社労士に給与計算の代行を依頼すれば、専門知識を持つ人材を確保する必要もなく、育成コストもかかりません。また、担当者が退職や異動しても、社労士が業務の流れを把握しているためスムーズに業務を引き継げます。
法律に準じた処理や法改正にも対応できる
給与計算は、法律に基づいた正確な処理が求められます。特に、休日出勤や残業手当の計算、付随する社会保険の手続きなどは法令に従う必要があり、誤った処理をすると企業のリスクにつながる可能性もあります。
社労士に給与計算の代行を依頼すれば、法律に準じた適切な処理が可能なだけでなく、給与計算に関連する法改正などにも迅速な対応が可能です。例えば、保険料率の変更や社会保険の加入対象の変更があった場合でも、抜け漏れなくしかるべきタイミングで最新のルールに沿った処理を行うことができます。
最近の税制改正や社会保険制度の見直しについては、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:【2025年最新】“パート扶養がなくなる”は誤解?年収の壁一覧とポイント整理)
労務・社会保険関連業務も任せられる
社労士に給与計算の代行を依頼すると、給与に関連する労働保険や社会保険など、以下のような手続きもスムーズに処理できるメリットがあります。
- 労働保険の年度更新
- 社会保険の算定基礎届
- 社会保険の加入・脱退手続き
- 労災給付
- 離職票の発行
給与計算と密接に関連する業務をまとめて依頼できる点は、社労士ならではのメリットです。また、労務相談や就業規則の見直しにも対応できるため、会社経営のよきパートナーとして依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
労働保険・社会保険については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:労働保険とは?労災保険・雇用保険との違いから加入条件をわかりやすく解説!)
(関連記事:社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!)
給与計算代行における社労士と税理士の違い
ここでは、社労士と税理士それぞれの違いや特徴をまとめました。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 社労士 |
|
| 税理士 |
|
上記のように、給与計算の代行を社労士に依頼した場合は、煩雑な労働・社会保険関連業務も依頼可能です。それぞれの違いを把握して自社にとってメリットが大きい方法を選んでみてください。
社労士に給与計算の代行を依頼する際の料金相場
社労士に給与計算の代行を依頼した場合の料金相場を解説します。料金は以下の要素によって変動するため、あくまで目安として確認してください。
- 従業員数
- 業務範囲(勤怠の集計、労働保険・社会保険の手続きを含めるなど)
- オプションサービス(給与明細の配信、専用封筒への封入など)
一般的な料金相場は、下記のとおりです。
| 従業員数 | 顧問料の相場 |
|---|---|
| 5人未満 | 2万円程度 |
| 10人未満 | 3万円程度 |
| 10~19人 | 4万円程度 |
| 20~29人 | 5万円程度 |
| 30~49人 | 6万円程度 |
| 50人以上 | 8万円程度 |
給与計算を行う人員の採用コストや賃金を考慮すると、社労士に依頼するほうがコストを抑えられる可能性があります。依頼する内容に応じて、具体的な料金を知りたい方は、社労士事務所に問い合わせてみましょう。
社労士に給与計算の代行を依頼する流れ
社労士に給与計算の代行を依頼する際は、一般的に以下の流れで行います。
- 「全国社労士検索」などで社労士を検索する
- 電話やメールで問い合わせる
- 面談・ヒアリングをする
- 提案・見積を確認する
- 契約を締結する
- 契約内容に基づき業務を開始する
※給与計算の代行を依頼する具体的な流れは、社労士によって異なる場合があります。詳細は問い合わせ先にご確認ください。
問い合わせや面談の際に、従業員数や業種、現状の処理方法や依頼したい内容などの情報を伝えられるように整理しておくと、スムーズに話を進められるでしょう。社労士によっては、労務相談や手続きなどといった顧問契約を結んでいる場合のみ給与計算の委託を受けているということもあるため事前に確認しておきましょう。
社労士に給与計算の代行を依頼する際のポイント
社労士に給与計算の代行を依頼するにあたって、いくつか準備をしておくと、スムーズに話が進みます。次の通り、事前に必要な情報を整理し、自社に適した社労士を選ぶことで、依頼後のトラブルも防げることでしょう。
- 依頼する内容や条件を定める
- 自社に適した社労士を選ぶ
- 提出する情報をまとめておく
それでは、それぞれのポイントについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
依頼する内容や条件を定める
社労士に給与計算の代行を依頼する際は、事前に内容や条件を整理しておくことが大切です。あらかじめ自社のニーズをある程度明確にしておくことで、スムーズに給与計算を依頼できます。
例えば、自社で活用している給与計算ソフトを通じて年末調整を行っている場合、給与計算ソフトの変更が必要になるとデータ移行の手間が発生してしまいます。
依頼後のミスマッチを防ぐためには、下記の要望についてまとめておくとよいでしょう。
- 利用している給与計算ソフトの確認、ソフトの貸与など
- 勤怠の集計、給与明細の配信などの依頼の有無
- 連絡方法(電話・メール・チャットツール)
- 労働保険、社会保険の手続きの依頼有無
- 年度更新、算定基礎届の提出の依頼有無
自社に適した社労士を選ぶ
給与計算の代行を依頼する社労士には、前項で挙げた内容や条件で依頼できるのかという点のほかに、自社にマッチしている社労士なのかという点も重要になります。
例えば、コミュニケーションの取りやすさは選ぶ際の重要なポイントです。担当者との相性をはじめ、問い合わせに対する応答速度や、わかりやすく丁寧なやり取りをしてもらえるかも確認してください。
また、自社の企業規模に対応していることや、業種に詳しいことも選定の材料になります。とくに、特定の業界に関する知識が豊富な社労士であれば、業界特有の労務管理や給与体系に精通しており、より適切なサポートを受けられる可能性が高まります。
提出する情報をまとめておく
給与計算の代行を社労士に依頼する際は、必要な情報を事前に整理しておくことが大切です。あらかじめ情報や書類をまとめておけば、打ち合わせや依頼をスムーズに進められます。
必要な情報の例としては、下記のものが挙げられます。
- 就業規則(給与計算に関わるルールを確認するため)
- 賃金規程(給与体系や手当の設定を把握するため)
- 従業員名簿(氏名・雇用形態・入社日などの基本情報を確認するため)
- 勤怠データ(出勤・残業・休暇の記録)
- 現在の打刻や給与計算の方法(使用しているシステムや計算フロー)
- 資料の提出方法(紙媒体、電子データ、クラウドサービスのどれを使うか)
必要な情報をそろえておけば、手続きがスピーディーに進みます。社労士との連携もしやすくなるので、事前にまとめておきましょう。
自社に合った給与計算の方法を見つけよう
社労士への依頼には、業務負担の軽減や人員コスト削減といったメリットがあり、専属担当者を配置できない中小企業や従業員数の多い企業では効果が期待できます。
自社内で給与計算を実施した場合の人件費やリスク管理といった、さまざまなコストを金額に置き換えて、依頼費用と比較検討することは難しい部分もあるかと思います。社労士事務所によっては初回無料相談を実施している事務所も多く存在しております。まずは漠然とした不安や改善要望を相談してから具体的に依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この日本最大級の社労士検索サイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談は無料の場合も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。