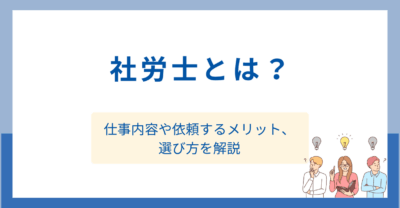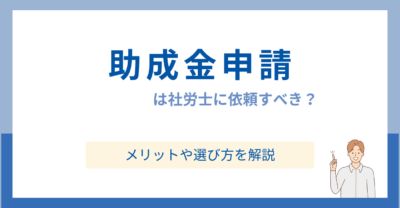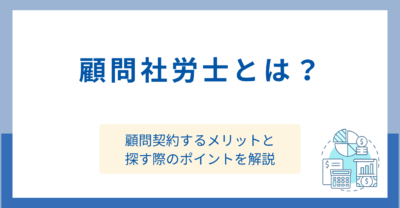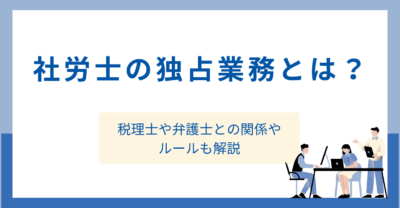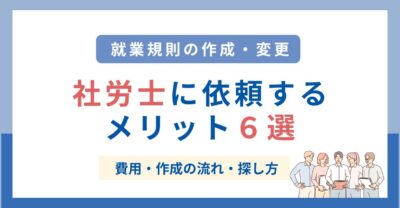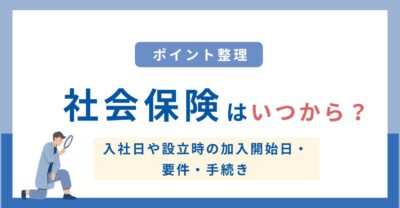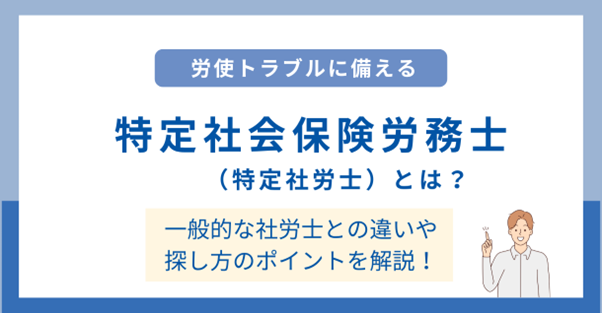
特定社会保険労務士(特定社労士)とは?一般的な社労士との違いや探し方を解説!
特定社会保険労務士とは、労使間のトラブルを裁判によらず話し合いで解決する場面で、企業の代理を行うことが認められた社労士です。
一般的な社会保険労務士(社労士)も労務相談や制度整備に幅広く対応しますが、労使間の法的な紛争において代理人として関与できるのは、特定社会保険労務士に限られます。
企業で起こりうる解雇・残業代・ハラスメントなどの労使間のトラブルは、初期対応を誤れば深刻化しかねません。そうした事態に備え、企業が“労使間のトラブルに対応できる専門家”と連携しておくことは、リスク管理のうえでも重要です。
本記事では、特定社会保険労務士の役割や通常の社労士との違い、探し方までを解説します。
特定社会保険労務士への依頼を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
特定社会保険労務士(特定社労士)とは

特定社会保険労務士とは、通常の社労士業務に加えて、労使間のトラブルが発生した際に“紛争解決手続代理業務”を行うことが認められている社労士です。
まずは、「紛争解決手続代理業務」について確認し、通常の社会保険労務士との違いについて整理しましょう。
紛争解決手続代理業務について
紛争解決手続代理業務とは、裁判によらず、当事者双方の話し合いによって解決を目指す「あっせん」「調停」「仲裁」などの手続きを代理人として行う業務を指します。
社会保険労務士法によりこの業務を行うことができるとされているのが『特定社会保険労務士』です。
特定社会保険労務士は、企業と労働者の間で、労働条件の不利益変更や解雇、配置転換など労働条件に関するトラブルが発生した際に対応が可能です。
※なお、労働組合と事業主の間の紛争や労働者同士の紛争は、対象外となります。
一般的な社労士との違い
特定社会保険労務士と通常の社労士との違いは、「紛争解決手続代理業務」が行えるかどうかにあります。
通常の社労士は、主に以下のような業務を担います。
- 社会保険や労働保険の手続き代行
- 就業規則や各種規定の整備
- 人事・労務管理の相談対応や制度設計コンサルティング
これに対して、特定社会保険労務士は、社労士としての一般業務に加え、労使関係のトラブルをADR(裁判外紛争解決手続)で解決する際に紛争当事者の代理人としての業務に対応が可能です。
特定社会保険労務士は、社労士の国家資格に加えて厚生労働省所定の研修と試験を経て、名簿に資格を付記することで認められます。
特定社会保険労務士が対応できる主な業務

特定社会保険労務士が対応可能な業務は以下の通りです。
- 都道府県労働局、都道府県労働委員会での個別労働関係紛争のあっせん申し立てに関する相談・手続き代行
- 都道府県労働局での障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法の調停手続等の代理
- 個別労働関係紛争の厚生労働省が指定する団体(民間の事業者)が行う裁判外紛争解決手続での当事者の代理(社労士単独で代理できる紛争目的価額の上限は120万円)
- 代理人としての意見陳述・和解交渉・和解契約の締結
以下、具体的な対応可能業務をご紹介します。
裁判外紛争解決手続に関する相談・手続き代行
特定社会保険労務士は、企業または労働者から裁判外紛争解決手続について相談に応じ、申し立てに必要な書類の作成や提出、手続きの進捗管理などを代理で行います。
あっせんは、企業・労働者いずれの立場からも申請可能です。
代理人としての意見陳述・和解交渉・和解契約の締結
裁判外紛争解決手続において、特定社会保険労務士は当事者の代理人として、以下の業務を行えます。
- 意見陳述
- 和解案の提示・交渉
- 和解契約書の作成・締結
これらの業務を通じて、当事者双方の主張を交互に聴きながら、適切な和解案を提案し、紛争を円満に解決へ導く役割を担います。
企業において特定社会保険労務士が必要になるケース

企業が労働者からあっせん申し立てを受けた際、初期対応を誤ると、紛争が長期化したり、法的リスクが拡大したりするおそれがあります。
以下のようなトラブルの場面では、特定社会保険労務士の支援が頼りになります。
■配転命令をめぐるトラブル
業務上の必要性から、やむを得ず社員に配転を命じたものの、社員が納得せず正当な理由なく拒否するケースです。
労働者側が「不利益な取扱い」や「嫌がらせ」と感じて、申し立てに至ることがあります。
■退職条件をめぐる交渉トラブル
退職に合意したものの、労働者から高額な退職金の上乗せを求められるケースがあります。
企業側が応じられない場合、労働者が不当な取扱いや説明不足を理由に申し立てを行うことがあります。
■給与減額に関するトラブル
業務上の重大なミスがあった社員に対して、賃金を減額した結果、「一方的な処分」「労働基準法に違反している」として抗議を受け、あっせん申し立てに発展するケースもあります。
これらの場面では、企業側では「正当な理由がある対応」と考えていても、労働者との認識のズレや説明不足によって申し立てにつながることが少なくありません。
こうしたトラブルが発生した際には、特定社会保険労務士が中立的な立場から状況を整理し、企業の適切な主張と和解交渉を支援することで、紛争を早期・円満に解決へと導くことが可能になります。
特定社会保険労務士の探し方

労使間の紛争は、円滑な話し合いによって早期に解決することが重要です。
そのためには、実績や対応力を見極めたうえで、信頼できる特定社会保険労務士を見つけておくことが欠かせません。
ここでは、特定社会保険労務士を見つけるための代表的な方法をご紹介します。
社労士専門のポータルサイトを活用する
最も効率的な探し方は、社労士に特化したポータルサイトを利用することです。
得意分野や実績、特定社会保険労務士の資格の有無など、必要な条件で比較・絞り込みができるため、自社に合った専門家を見つけやすくなります。
なかでもおすすめなのが、全国6,000以上の社労士事務所が登録する「社労士ナビ」です。
以下のような条件で、ニーズに合った特定社会保険労務士を絞り込んで検索できます。
- 「あっせん代理が得意な社労士一覧」から特定社会保険労務士のみを表示
- 地域(都道府県・市区町村)や相談分野・対応可能業界での絞り込み
- 得意分野(あっせん、就業規則、助成金など)で検索
- 初回相談無料の有無
複数の事務所を比較しながら、対応姿勢や説明の分かりやすさを確認できるため、ミスマッチのリスクを避けて安心して依頼先を選ぶことができます。
同業者や取引先から紹介を受ける
同じ業種の企業や、顧問の税理士・弁護士などから紹介を受ける方法も有効です。
同業者や取引先が過去に特定社会保険労務士と連携し、トラブルを円満に解決した実績がある場合、その経験をもとに信頼できる専門家を紹介してもらえる可能性があります。
ただし、紹介を受けたからといって、必ずしも自社に合うとは限りません。
業種や組織規模、対応してほしい課題の内容によって、求められる専門性や支援スタンスは異なるため、面談を通じて実務対応力や相性を確認することが大切です。
労働局や公的な相談窓口を利用する
都道府県労働局や社会保険労務士会、商工会議所などの公的窓口でも、必要に応じて専門家を紹介してもらえることがあります。
ただし、紹介を受けただけで即依頼するのではなく、実際に面談を行い、自社の課題に対して的確に対応できるかどうかを見極めることが大切です。
まとめ|自社に合った特定社会保険労務士探しなら「社労士ナビ」がおすすめ
本記事では、特定社会保険労務士の制度概要や一般的な社労士との違い、あっせん手続きにおける具体的な対応業務、探し方のポイントまでを解説しました。
特定社会保険労務士は、紛争が起きた際の“当事者の心強い代理人”となるだけでなく、再発防止や制度見直しなどの支援においても頼れる存在です。
法的トラブルの対応力と労務管理の専門性を兼ね備えた特定社会保険労務士と連携することで、企業はより安定した労務管理の体制を築くことができます。
特定社会保険労務士に相談する
特定社会保険労務士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。