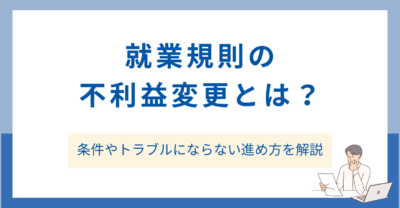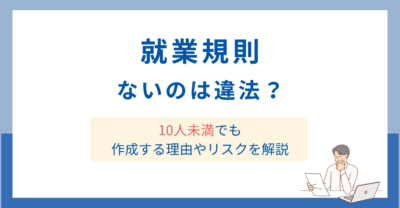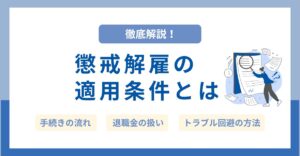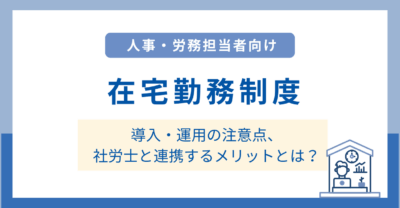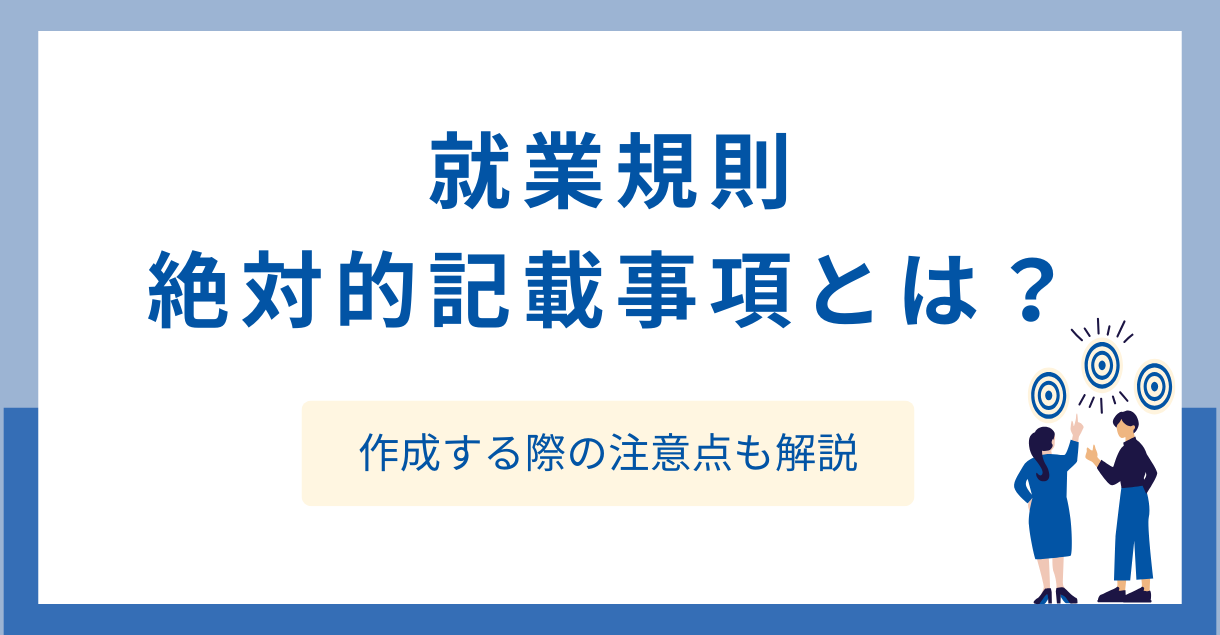
就業規則の絶対的記載事項とは?作成する際の注意点も解説
就業規則の作成、何から手をつければいいか迷っていませんか。実は、就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、怠ると法律違反になることもあります。
本記事では、労働時間、賃金、退職など、絶対的記載事項の内容を詳しく解説し、相対的記載事項や任意的記載事項など、就業規則作成の全体像を網羅的に説明します。この記事を読めば、就業規則の概要を理解でき、不備によるトラブルを未然に防ぐことが可能です。
就業規則に記載すべき内容が判断できるため、これから就業規則を作成される方や変更を検討中の方はぜひ、参考にしてください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
就業規則の記載事項は主に3つ
就業規則の記載事項は、大きく3つに分けられます。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
就業規則は、法律に基づいて作成する必要があります。適切な手順で作成し、企業の実態に即した内容とすることが重要です。記載事項をここで確認し、正しい就業規則を作成しましょう。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、就業規則に必ず記載しなければならない内容であり、大きく3つに分類されます。
- 労働時間について
- 賃金について
- 退職について
それぞれの内容を詳しく解説するので、内容を把握していきましょう。
労働時間について
絶対的記載事項の労働時間に記載しなければならない内容の例を表にまとめました。
| 絶対的記載事項(労働時間関係) | 主な記載事項 |
| 始業および終業時刻 |
|
| 休憩時間 |
|
| 休暇 |
|
| 交替制の就業時転換に関する事項 |
|
所定労働時間は、労働基準法では原則として1日8時間・週40時間が上限(法定労働時間)ですが、以下の例外もあります。
- 管理監督者(労基法第41条)・管理監督者(管理職)は、労働時間・休憩・休日の規制が適用されません。ただし、深夜労働(22時~5時)の割増賃金は必要です。
- 小規模事業場の特例(労基法第131条)・常時10人未満の事業場(商業・サービス業など)は、労使協定を結べば週44時間まで延長可能です。
- 変形労働時間制の導入(労基法第32条の2・3)・変形労働時間制(1ヵ月単位・1年単位・フレックスタイム制など)を導入すれば、特定の日に8時間を超えて労働時間を設定可能です。
上記に該当する、または適用する場合は、就業規則への明記のほか、労使協定の締結が必要なものもあるため、注意が必要です。
賃金について
絶対的記載事項の賃金は、以下の内容を定める事項です。
| 絶対的記載事項(賃金関係) | 主な記載事項 |
| 賃金の取り決め |
|
| 賃金の計算および支払い方法 |
|
| 賃金の締切および支払時期 |
|
| 昇給に関する事項 |
|
なお、対象となるのは定期的に支払う賃金であり、臨時に支払われる賃金(賞与)等は含まれません。また、源泉徴収税や住民税などを賃金の控除に含める場合もありますが、法律上控除されるものであるため、記載の義務はありません。
退職について
退職については以下のとおりです。なお、懲戒解雇については、解雇に記載すべき事項ではなく任意的記載事項の「表彰・制裁」に記載する場合が多いため、ここでは含めずに主な記載事項を紹介します。
| 絶対的記載事項(退職・解雇関係) | 主な記載事項 |
| 定年退職 |
|
| 退職(定年退職以外) |
|
| 解雇 |
|
それぞれ重要な内容ですが、解雇については法令の解釈や適用に誤りがあると、トラブルに発展する可能性がとくに高いため、正確かつ正当な内容を記載しましょう。
また、多くの企業が独自のルールを就業規則に含めている場合もあるため、法律を下回らないよう注意が必要です。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、制度を設ける場合において必ず記載しなければならない事項を指します。内容例は以下のとおりです。
- 退職手当が適用される労働者の範囲
- 退職手当の決定・計算・支払時期、支払い方法
- 臨時の賃金
- 労働者が負担する作業用品や事務用品、食費など
- 安全・衛生
- 職業訓練
- 災害補償・業務外の傷病扶助
- 表彰・制裁の種類や程度
- 退職時の手続き方法
退職金や職業訓練など、法律で定められていないものを会社で定める場合に、相対的記載事項が必要になります。しかし、どのように定めれば良いのか判断が難しく、専門的な知識が必要な部分ともいえるでしょう。
就業規則を作成する際は、専門家である社労士への依頼がおすすめです。社労士であれば、絶対的記載事項や相対的記載事項の具体例を踏まえ、スムーズに作成してくれます。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、法的に記載を必須にしているものではなく、会社が独自に定める内容を記載する事項です。記載例として、次のものが挙げられます。
- 就業規則の適用範囲
- 服務規律
- 休職
- 採用
- 異動
- 身元保証
- 試用期間
- 時間外労働(残業)
- 損害賠償
任意的記載事項は、服装や髪型などの身だしなみや異動に関する規定など、会社独自のルールを法律の範囲内で定めるものです。そのため、会社のイメージや利益だけでなく、従業員にとっても納得できるように内容を考えてみてください。
就業規則を作成する際の注意点・ポイント
就業規則を作成する際は、絶対的記載事項をはじめとするさまざまな注意点もあるため、以下を確認しましょう。
- 法律の基準を下回らない
- 従業員代表者の意見を聴く
- 事業場の実態に合わせる
- わかりやすく明確に記載する
- 定期的に見直す
法律の基準を下回らない
就業規則の内容は、労働基準法や労働安全衛生法などの法律に違反してはならないため、法律で定められた基準を下回らないよう、注意が必要です。具体的には、以下のような例が挙げられます。
- 所定労働時間が9時間以上とされている
- 年次有給休暇日数が少ない
- 減給処分の金額が1日分の給与の半分を超えている
また、従業員が行う副業に対し、会社から法的に制限をかけることはできませんが、業務に支障をきたす場合は、制限することができます。副業について就業規則で定める際も、法律の基準を把握した上で正しい内容を記載すると、従業員が納得できる就業規則の作成が可能です。
従業員代表者の意見を聴く
就業規則を労働基準監督署に提出する際は、原則「従業員の過半数代表者」からの意見書を添付しなければなりません。意見書取得手続きを行わずに就業規則を届け出ると、受理されないケースもあるため注意が必要です。
円滑な会社経営には、従業員との関係が良好であることもひとつの要素であることから、従業員から理解を得ることも大切です。意見書を通じて就業規則案の修正を行うことで、会社の方針を明確に定めつつ、従業員が納得できる就業規則を作成しましょう。
就業規則の意見書の書き方や、従業員代表者の選出方法などを下記の記事にて解説しているので、参考にしてください。
就業規則の意見書とは?記入例や作成時のポイントや注意点を解説
事業場の実態に合わせる
就業規則を作成する際は、事業場の実態に合わせて作成してください。就業規則を作成する場合、多くの時間と労力を要するため、インターネット上などで入手したひな形をそのまま使いがちです。そのまま使用すると、思わぬ労使トラブルの原因につながる場合があります。
しかし、専門的な知識がないと作成が困難であることも事実です。そのため、就業規則を作成する際は、専門家である社労士への依頼がおすすめです。
わかりやすく明確に記載する
就業規則を作成する際は、内容を明確に記載しましょう。あいまいな表現や抽象的な表現はトラブルにつながる可能性があります。
例えば、勤務時間や休憩時間について記載する場合は、以下のような内容が望ましいです。
(具体例)
第〇条(所定労働時間)
1. 従業員の所定労働時間は実働8時間とし、始業・終業の時刻は以下の通りとする。
始業時刻:午前9時00分
終業時刻:午後6時00分
休憩時間:午後12時00分から午後1時00分まで
2. 会社は業務上の必要性がある場合、第1項の始業・終業時刻を繰り上げ、または繰り下げることがある。その場合、前日までに従業員に通知する。
就業規則に記載する内容は誰が読んでも同じ解釈になるよう、文章も考えなければなりません。
作成が困難な場合は、専門家である社労士に依頼しましょう。
定期的に見直す
就業規則をよりよいものにするポイントとして、作成した後は定期的な見直しがおすすめです。法令が変更された際は該当箇所を変更しなければならないほか、コロナ禍で多くの企業に導入されたテレワークのように、会社の状況に応じた改定が必要です。
また、就業規則とともに雇用契約書の変更が必要になるケースもあり、片方の更新を忘れると相違する事項が生じてしまいます。就業規則を見直す際は、内容にかかわるほかの書類や会社のルールも同時に見直しましょう。
就業規則を作成する際は社労士に相談しよう
就業規則は、会社と従業員を守る大切なルールブックです。作成する場合、労働時間や賃金、退職に関する「絶対的記載事項」は、必ず記載しなければなりません。
漏れがあると、労働基準法に違反したり、従業員とのトラブルに発展したりする可能性があります。作成するには時間と労力が必要になります。そのため、就業規則を作成する際は社労士に相談しましょう。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。